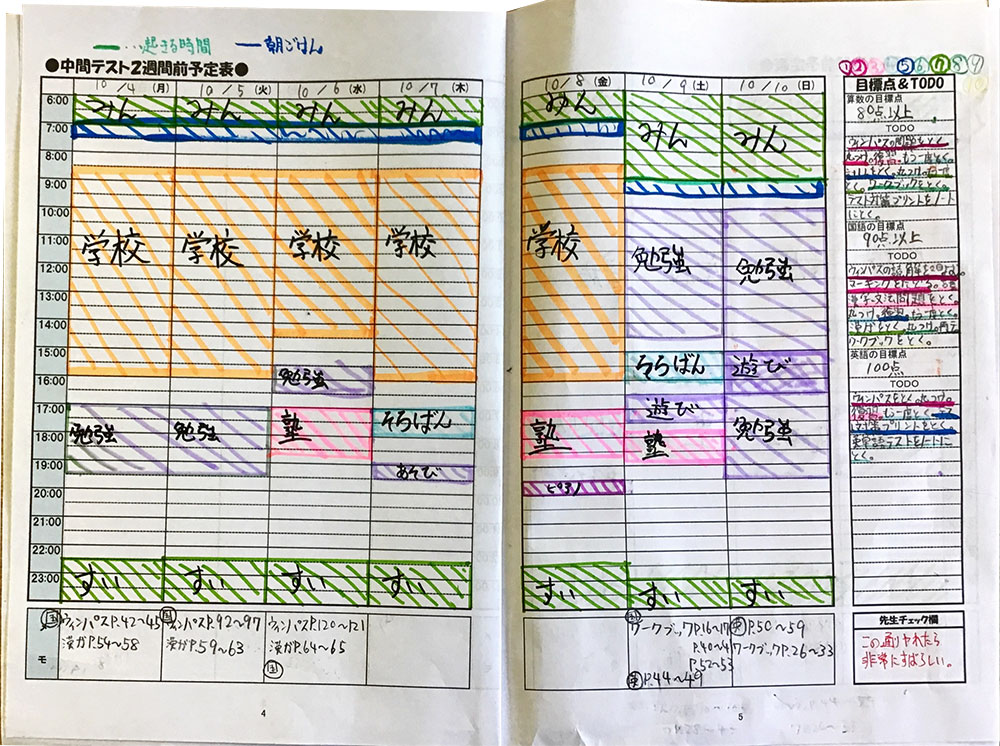青翔中学校 令和5年度(2023年度)の出題形式について
青翔中学校
令和5年度(2023年度)出題形式
適性検査1:国語
1.「理系」色の文章における論理的読解・作文が試される
傾向は変わらず、「理系」色が強い内容の文章を素材とし、設問も「論理的読解」を求めるものでした。
作文については、以前も「観察」「実験」など「理系色」がありましたが、 2023年度においては「資料を読んでの理科系レポート作成」というような内容であり、より一層「理系色」が強くなっている。
2.知識問題・作文問題の重要性
「知識系」といえる設問は2題ですが、作文以外の設問数が5題であることを考えると、知識系で確実に得点することは重要。
作文については、「自由に自分の考えを書く」というものではなく「正しく資料を読み取って書く」というものであり、「正解・不正解」がはっきり分かれる作文です。
★国語領域の問題は大問2
(適性検査1 100点満点(40分) / 国語領域50点・社会領域50点)
| 本文内容 | 論説文(進化の謎を解く発生学」田村宏治より)内容:「研究(実験)の意義・楽しさについて」の説明 |
|---|---|
| (一) | 漢字の部首 |
| (二) | 指示語の内容説明(記述) |
| (三) | 本文の空欄補充〔内容理解+四字熟語知識〕(選択肢) |
| (四) | 傍線部の理由(文章中から抜き出し) |
| (五) | 傍線部の内容説明(文章中から抜き出し) |
| (六) | 作文:資料を読み取り「半熟卵と温泉卵のちがい」「温泉卵の作り方」について書く。(140字以上160字以内) |
適性検査2:算数
今年から試験時間が40分から50分に伸びましたが、小問数は例年と大きく変わりませんでした。
(2021年度→12問、2022年度→9問、2023年度→11問)
ただし、問題文が非常に長くなっており、読解力が求められるようになりました。
そのため、時間的な余裕はそこまで変わらず、問題に書かれている会話文の中から必要な情報を見つけ、素早く解くことが求められました。
また、奈良女子大学附属中等教育学校と同様に、途中の式や説明を書く問題が出されます。
青翔中学校は公立の適性検査型としては、比較的易しいレベルの問題を扱う中学校です。
ただし、問題文をきちんと読み込み、またそこから問題を解くヒントなどをつかまなければならないのは、他の適性検査型の入試と同様です。
近年、特殊算と呼ばれるような小学校では習わない問題も出されるようになり、問題の難易度は上がってきています。
普段から、受験算数の問題を取り組んできた生徒にとっては目新しい問題ではないですが、受験算数の問題を取り組んでこなかった生徒にとっては、難しい内容になっています。
また、奈良県の公立高校入試の数学の問題のように、別の方法での解き方を考えさせる問題もよく出されます。
★算数領域の問題は大問1~大問3
(適性検査2 150点満点(50分) / 算数領域75点・理科領域75点)
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 3 | 暦算(1)2月と3月が同じ曜日になる理由(選択問題)(2)2023年6月1日の曜日(3)2029年1月1日の曜日 |
| [2] | 4 | 角柱と円柱(1)水の深さ(説明あり)(2)比例の関係(3)反比例の関係(一部選択肢あり)(4)角柱と円柱の性質(選択問題、説明あり) |
| [3] | 4 | 資料の調べ方(1)平均値(2)柱状グラフ(選択問題)(3)累積度数のグラフ(選択問題、説明あり)(4)グラフの特徴(選択問題) |
適性検査2:理科
全8問中、記述問題が4問、記号選択問題が4問でした。
記述問題も実験方法を説明する問題が2問、現象の理由を説明する問題が2問でした。
また、記号選択の問題も実験結果や資料を読み取り、そこから分かることを選ぶ問題が多く、普段の演習から「なぜ?」を考えて説明する練習をしておかないと解くのが難しくなってきます。
また、実験方法を説明したり、実験方法などをヒントにしながら、資料の意味を読み取ったりする必要があるため、1問1問に時間がかかります。
昨年より試験時間は10分長くなっていますが、時間配分にも十分注意して問題を解く必要があります。
★理科領域の問題は大問2 小問8問。
(適性検査2 150点満点(50分) / 算数領域75点・理科領域75点)
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [4] | 4 | (1)ほとんどの「畝」を南北にまっすぐになるように作る理由を選ぶ問題(2)北側に背の高い植物を植え, 南側に背の低い植物を植えると, どの植物もそろって成長する理由を説明する問題(3)アサガオの種子の発芽に「空気」と「水」が必要であることを確かめる実験方法を、図と文章で説明する問題(4)実験結果からわかる、アサガオの花をさかせるのに必要な条件を選ぶ問題 |
| [5] | 4 | (1)最初に出てきた気体を集めない理由を説明する問題(2)発生した気体の重さをはかる実験方法を説明する問題(3)実験2の結果から、加えた重曹の重さと発生した気体の関係について分かることを説明した文のうち、まちがっているものを選ぶ問題(4)実験2の結果をもとに、重曹だけを水にとかしたときの水の温度がどのようになるかの予想と、根拠となったグラフを選ぶ問題 |
適性検査1:社会
知識問題に加え、資料を読み取り分析する力が求められる問題が出されました。
記述式の問題が無くなりましたが、問題文で問われている内容をしっかり読み取る力が求められます。
(1)と(2)は日本の気候区分と本州四国連絡橋の名称だけではなく適合する場所も問われます。
このため知識の暗記だけではなく総合的な理解力が必要となります。
(7)は表の数字を分析し、さらに割合を計算するという従来とは異なる形式の問題が出題されます。
★社会領域の問題は大問1
(適性検査1 100点満点(40分) / 国語領域50点・社会領域50点)
| 大問番号 | 小問数 | 出題内容 |
|---|---|---|
| [1] | 7 | (1)札幌市、上越市、高松市の雨温図の中から高松市を選択する問題(2)本州四国連絡橋の3つのルートから、岡山県を通るルートを選択する問題(3)歌舞伎が広まったころ(江戸時代)の文化の説明として適切なものを選択する問題(4)非核三原則の内容を答える問題(5)高松市の3枚の地図を、資料を参考にして古い順に並べ替える問題(6)塩田での塩の生産量を示すグラフの読み取りとして、適切なものを選択する問題(7)四国4県の農産物産出額の資料を読み取り、米の産出額がその県の合計産出額に占める割合の最も低い県名を書き、さらに四国4県の中で果実の産出額が最も高い県について、野菜の産出額がその県の合計産出額に占める割合を計算して、求める問題 |
適性検査3
1グループ6~7名(男女混合)、30分間で実施。30点満点。
「科学者が考える日常の不思議」について述べた文章の朗読が1回放送され(メモ可)、その後発問がある。
| 内容 | |
|---|---|
| 問題① | 解答用紙に放送内容を要約して書く。 |
| 問題② | あなたが考える「日常の不思議」や「科学者の思考」について発表しなさい。発表にはそう考える理由も含めること。 |
| 問題③ | 一番良かった人の意見とその理由を発表しなさい。 |