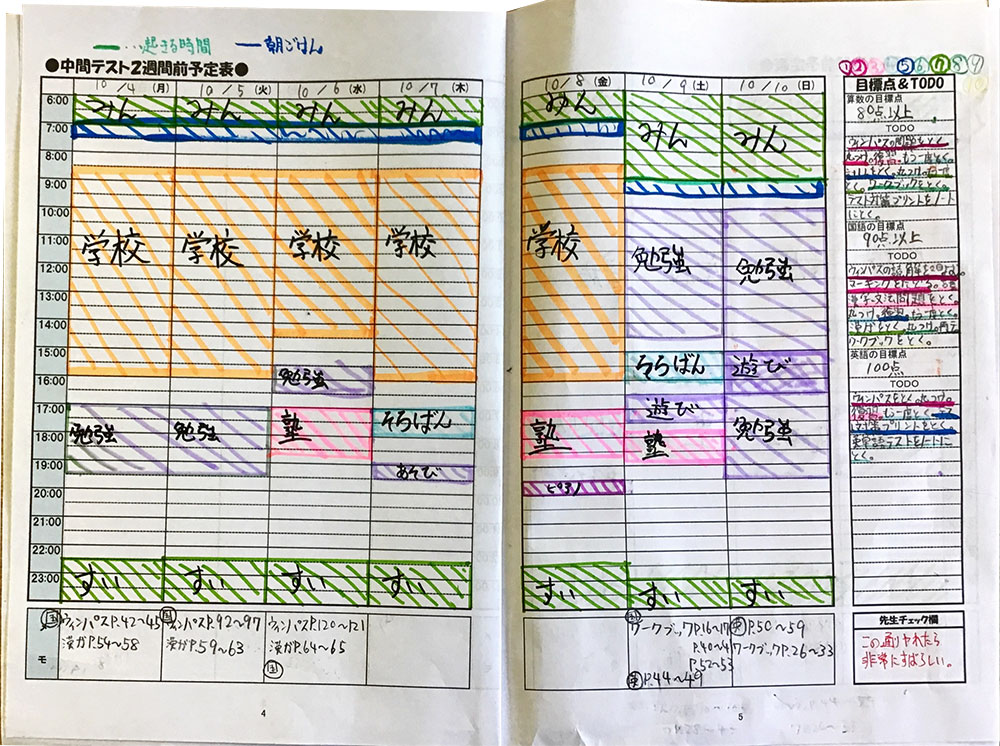一条高等学校附属中学校 令和7年度(2025年度)の出題形式ついて
一条高等学校附属中学校
令和7年度(2025年度)出題形式
適性検査Ⅰ(国語)
「適性検査Ⅰ」全体として、2024年度と同じく「大問3問構成(大問1:国語/大問2:社会/大問3:国語・社会融合問題)」でした。
また、「検査Ⅰ全体のボリューム」「国語と社会の設問比率」ともに、2024年度と大きく変わっていません。
1.本文内容を「細かいところまで」「正確に」読み取る力が求められる
設問数は2024年度からの大きな変化はありませんが、下記のような出題があり、高得点を取るためには「本文内容の正確な読み取り」が必要です。
大問1・問四:傍線部を含む段落にも「解答の材料らしきもの」はありましたが、「正しい材料」は違う段落にありました。
かつ、指定字数に合わせて「材料の言い換え」が必要でした。
大問3・問一:「こういうこと」という指示語の指示内容を選ぶ問題でしたが、傍線部の「前の内容」「後の内容」の関係を理解し、「指示内容は傍線部の(前ではなく)後ろである」と判断することが必要でした。
2.「知識系」設問の出題なし
「知識系」の問題については、2022年度は「部首名」「画数」、2023年度は「三字熟語の組み立て」が出題されましたが、2024・2025年度は出題がありませんでした。
3.作文問題は「難化」
4年連続「空所補充をして題名を決める」「第一段落は『経験』を書く」「第二段落は『考え』を書く」「120字以上150字以内」という出題でした。
ただし、2025年度は初めて「筆者の考えに沿った内容で書く」という条件がつけられました。
これによって「本文内容の理解」「本文内容にあった題名・経験の設定」という、過去3年よりも高度な思考が必要となりました。
国語領域は大問1と大問3の問一・三(適性検査Ⅰ 100点満点・45分)
| 大問 | 小問 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 本文 | 論説文(「さくらさんが『自己肯定感』の在り方について考えるために読んだ」という設定で、文章を提示) 文章:毛内拡『「気の持ちよう」の脳科学』より 内容:自己肯定感の本質について論じるとともに、「自己効力感」の重要性を説く内容 |
| 問一 | 漢字の書きとり問題(2問) | |
| 問二 | 本文中の二か所の空所に入る接続語の組み合わせ(選択肢問題) | |
| 問三 | 傍線部に関して筆者が述べていることの把握(選択肢問題) | |
| 問四 | 傍線部に関して筆者が述べていることの把握(記述問題・40字以上50字以内) | |
| 問五 | 本文内容を整理した図の空欄補充(2問・選択肢問題) | |
| 問六 | 作文問題 「自分は( A )ができる。それは、( B )のおかげだ。」という題名(空所は自分で考える)の作文 ・筆者の考えに沿った内容で書く ・第一段落は題名に関する経験を書き、第二段落は第一段落に書いた内容をふまえての考えを書く ・120字以上150字以内 | |
| 3 | 本文 | 論説文(「はじめさんが『地域』の特徴を考えるために読んだ」という設定で、文章を提示) 文章:山下祐介『地域学をはじめよう』より 内容:社会を「社会有機体(=ひとつの生命体)」としてとらえた上で、「地域」を論じる内容 |
| 問一 | 指示語が指す内容(選択肢問題) | |
| 問三 | 傍線部の言い換え(書き抜き問題) |
適性検査Ⅱ(算数)
2024年度と同様に大問数が3問で、小問数は算数は6問でした。
ただし、算数で記述が必要な問題は出ませんでした。
また、問題自体の難易度や出題傾向には大きく変更はありませんでした。
公立中の適性検査型としては、比較的易しいレベルの問題であり、受験生の中には満点を取っている人もいると考えられます。
ただし、解くのに時間がかかる問題も多く、素早く情報を読み取り時間配分に注意する必要があります。
2024年度と比較すると、全体的に難易度が若干上がりましたが、比較的解きやすい問題も多く、普段、受験算数の問題を取り組んできた生徒にとっては授業で得た知識を活用して解くことができたと思われます。
適性検査Ⅱ《算数・理科的問題》(100点満点・45分) 大問3問、小問16問(算数6問、理科10問)
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 問1 (1)(2)規則性(硬貨の合計金額を求める問題) |
| 問2 (1)(2)円の移動(円の中心が動いた長さを求める問題) | ||
| 問3 (1)差集め算 (2)条件整理(選択問題) |
適性検査Ⅱ(理科)
2024年度と同様に大問数3問、理科の小問数10問でした。
問題構成としては、2024年度は記述問題が2問と減少し、図で表す問題が1問出題されましたが、2025年度は記述問題が3問、計算問題が2問、グラフを作成する問題が1問出題されていました。
記述問題の特徴としては、実験方法を説明する問題はなく、実験中に行う操作の理由や、現象の理由を説明する問題でした。
また2024年度同様、資料や実験結果から考える問題が多数出題されており、資料やグラフ、実験結果から分かることなどを読み取る力が必要な問題でした。
なお、2025年度は記述問題が1問増えただけでなく、計算問題も出題されたため、時間配分も重要でした。
適性検査Ⅱ《算数・理科的問題》(100点満点・45分) 大問3問、小問16問(算数6問、理科10問)
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 問1 ふりこが1往復する時間を測定するために10往復する時間を測定した理由を説明する問題 |
| 問2 実験結果の表の空欄にあてはまる数を選ぶ問題(2問) | ||
| 問3 ふりこの長さとふりこが1往復する時間の関係のグラフを選ぶ問題 | ||
| 問4 1往復する時間が6秒のふりこの長さを選ぶ問題 | ||
| 問5 長さ100cmのふりこの支点の真下50cmのところにくぎを打ち、ふりこが1往復する時間を計算で求める問題 | ||
| 問6 金属でできたふりこ時計のふりこが、夏の暑い日に1往復するのにかかる時間が長くなる理由を説明する問題 | ||
| 3 | 4 | 問1 4月12日の気温を、折れ線グラフに表す問題 |
| 問2 与えられた公式を使って、不快指数を計算する問題 | ||
| 問3 さくらさんが指摘した内容に当てはまる文を書き、文を完成させる問題 | ||
| 問4 「夕焼けの翌日は晴れ」と予想される理由を説明する問題 |
適性検査Ⅰ(社会)
大問二は国土や世界の国などに関する地理分野と、江戸時代から大正時代に関する歴史分野の融合問題で、資料の読み取りと知識を結び付ける問題が中心です。
大問三は国語との融合問題であり、明治時代や政治に関する知識が求められました。
社会領域は大問2と大問3の問二・四・五 (適性検査Ⅰ 100点満点・45分)
| 大問番号 | 小問番号 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 問一(一)奈良市とパリ市を表した雨温図を見て、奈良市の雨温図を選択する問題 |
| 問一(二)会話文中の空欄にあてはまる、対馬海流以外の暖流の海流名を答える問題 | ||
| 問二 浮世絵の特徴を説明した文の、空欄に当てはまる言葉を3字~6字で答える問題 | ||
| 問三 1900年から1924年の間のできごととして、適切なものを選択する問題 | ||
| 問四 人口やGDPなどの上位を表す表や、会話文に当てはまる言葉を答える問題 | ||
| 問五 ロサンゼルスと日本の飛行時間について、行きと帰りではどちらが所要時間は短いかを風との関係性から答える問題 | ||
| 3 | 3 | 問二 本文の第4段落の内容をまとめた図に当てはまる言葉を答える問題 |
| 問四 明治時代に起こったできごとの説明として、適切なものを選択する問題 | ||
| 問五 明治時代以降の産業と地域の特ちょうをまとめた文の、空欄に当てはまる言葉を答える問題 |
面接
1グループ5名(男女混合)での実施。(30点満点・20分程度)
| 内容 | |
|---|---|
| 集団面接 | 面接官3名。質問は3問 ① 自分のよい所(1番から順にあてられる) ② 中学校で、 特に力を入れてがんばりたいこと(5番から順にあてられる) ③ 手紙を書くならだれに書くか理由とともに答える(挙手制で発表する) |