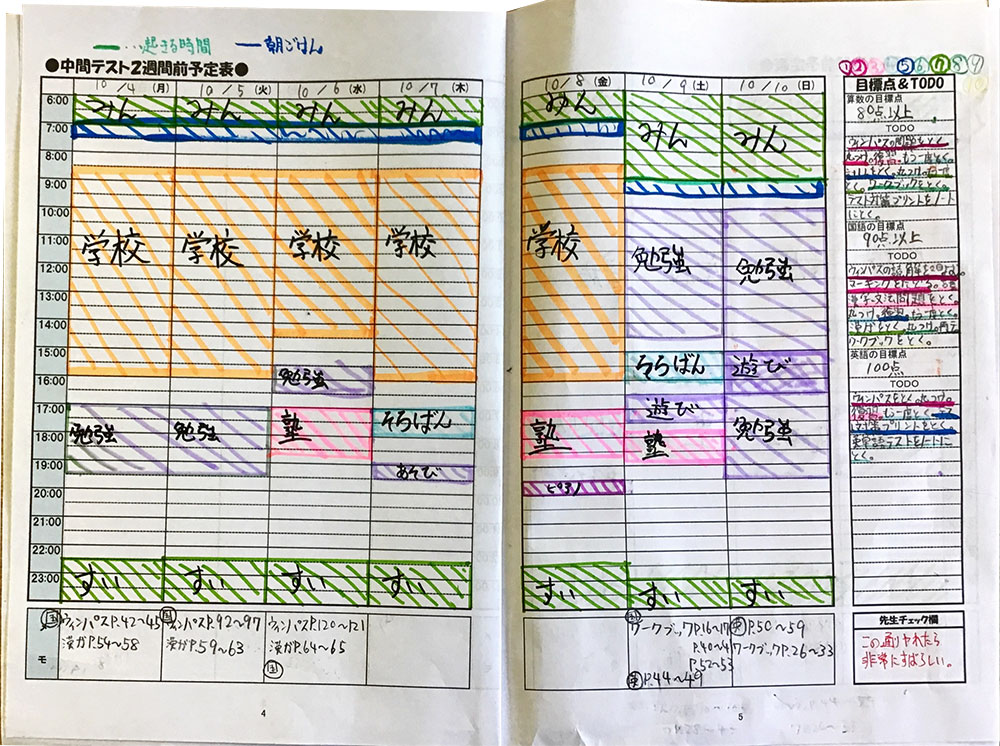奈良教育大学附属中学校 令和6年度(2024年度)の出題形式について
奈良教育大学附属中学校 令和6年度(2024年度)出題形式
【国語】
1.内容・難易度は2023年度と変化なし/「『知識領域』・『問われ方』への対応力」が求められる
2022年度から2023年度で「読解問題が2題から1題へ」「作文問題(240字~300字)を出題する」という大きな変化がありましたが、2024年度の問題は「問題数」「小問の内容」など、細かい部分まで2023年度と酷似していました。
知識領域については、2023年度が「敬語」「熟語の構成」、2024年度は「助動詞・助詞」「ことわざ・慣用句」が出題され、「知識分野全体から何かを出題する」という方針であると考えられます。
読解問題については、(4)~(7)のように「論旨把握を試す設問」という共通点はありながらも「質問の仕方(問われ方)」に変化を持たせています。
2.「自分の考え」を複雑な条件のもとで書かせる作文問題
作文問題は、2023年度(「コミュニケーションについての自分の考え」を書く)に続いて、「自分の考えを書く」というタイプの出題でした。
「おすすめの本」についての作文でしたが、条件で二段落目の内容が細かく指定されていたため、「こういうところが面白いから、この本をおすすめする」といった単純な理由では書けないような出題になっていました。
30点満点(40分)
| 大問1 | (1) | 漢字書き取り(2問) |
| (2) | 漢字の読み(2問) | |
| (3) | 助動詞・助詞の知識(「だ」「られる」「の」の意味識別・3問) | |
| (4) | ことわざ・慣用句の完成(空所に入る動物名を答える・3問) | |
| 大問2 | 本文内容 | 論説文(森毅『まちがったっていいじゃないか』より) 内容:「自分を大事にする」「目的にしばられない」という観点で現代社会を生きるためのヒントについて述べる内容 |
| (1) | 脱文補充(設問で提示された一文が本文中のどこに入るかを段落番号で答える) | |
| (2) | 同内容表現(傍線部と同内容の表現を本文中から書き抜いて答える) | |
| (3) | 接続語の補充(選択肢問題・3問) | |
| (4) | 論旨把握(傍線部に対しての筆者が感じていることを書き抜いて答える) | |
| (5) | 論旨把握(傍線部の原因や指示語内容をおさえる・選択肢問題) | |
| (6) | 論旨把握(本文内容を整理した文の空所に当てはまる言葉を、本文中から書き抜いて答える・4問) | |
| (7) | 論旨把握(5つの選択肢中から「本文で筆者が述べていなこと」を全て選ぶ) | |
| 大問3 | 作文 | これまで読んだことのある本について「私のおすすめの本」という題名で作文する。 ・二段落で書く 第一段落は「本の紹介」を書く。 第二段落は「どのような人におすすめできるか」あるいは「どんなときに読むことをすすめられるか」、「その理由」を書く。 ・240字以上300字以内 |
【算数】
2020年度から出題傾向が変わったことによって、大問数が9問から6問と大幅に減り、1問の配点が大きくなりました。
問題の難易度については、標準的なレベルの問題も多く出されており、比較的単純な解法で解くことができる問題もあります。
毎年、図形の作図の問題やさまざまなグラフの作図の問題が出されています。
2024年度は、 図形の作図と図形が重なった部分の面積と時間を表すグラフの作図が出題されました。
2020年度 棒グラフの作図、展開図の作図、水量変化とグラフの作図
2021年度 正三角形の作図、棒グラフの作図
2022年度 棒グラフの作図、速さとグラフの作図
2023年度 2量の関係を表すグラフの作図
2024年度 問題の考え方を説明するための図形の作図、 図形の移動とグラフの作図
また、図形の問題は毎年レベルの高い問題も多く出されているので、そこで得点を取ることは難しいと思われます。
2024年度も大問4と大問5の(2)の問題は難易度が高く正答率が低かったと思われます。
よって、解ける問題を確実に正解することが、合格ラインを超えるうえで、非常に重要なポイントになります。
30点満点(40分)
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 5 | 計算問題 |
| [2] | 4 | 小問集合 |
| [3] | 3 | 規則性(等差数列) |
| [4] | 3 | 平面図形(図形の作図の問題あり) |
| [5] | 2 | 立体の切断 |
| [6] | 3 | 図形の移動とグラフ(グラフの作図の問題あり) |
【総合:理科】
2024年度も、2023年度同様大問が6問ありました。
また、小問が14問(うち記述問題1問)となり、2023年度の11問よりやや増加しました。
2023年度同様、資料をもとに意見を書く記述問題もあり、資料の意味をつかみ自分の意見をまとめて書くという点では、少し考えづらい問題だったと思われます。
普段から、資料をもとに自分の考えをまとめる練習が必要です。
またそのほかにも、大問2は図を用いて考える問題、大問3・大問4はグラフを用いて考える問題など、図やグラフを用いた問題も多く出されます。
総合(理科と社会に分かれる)で60分、30点満点。
理科領域:大問6問、 小問14問。理科にかけられる時間は30分程度で15点満点。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 2 | (1)水の循環についての説明文中の空欄に入る語句の組み合わせとして正しいものを選ぶ問題 (2)「水蒸気が冷やされて水滴になる」のと同じ現象をすべて選ぶ問題 |
| [2] | 1 | A~Dの会話から、A~Dがどの地点で観測しているかを選ぶ問題 |
| [3] | 4 | (1)グラフから考えられることをすべて選ぶ問題 (2)グラフより、水100mLに17gの粉末をとかすには何℃以上にする必要があるかを選ぶ問題 (3)グラフより、水温を20℃まで下げたとき、出てくる結しょうの量を選ぶ問題 (4)加熱するときに用いる実験器具を4つ選ぶ問題 |
| [4] | 3 | (1)ソメイヨシノの花の断面を選ぶ問題 (2)問題文のヒントとグラフより、サクラの開花日を予想して選ぶ問題 (3)ソメイヨシノの開花と、標高や緯度との関係を選ぶ問題 |
| [5] | 3 | (1)空気の入った筒の中に、空気でふくらませた風船を入れ、おしぼうで筒の中の空気を押したとき、筒の中の風船の大きさの変化を選ぶ問題 (2)(1)の風船の中身を水に変え、おしぼうで筒の空気を押したとき、おしぼうと風船がどのようになるかを選ぶ問題 (3)ソケットのない豆電球を光らせるために、導線につなぐ部分を選ぶ問題 |
| [6] | 1 | 外来生物であるアメリカザリガニをどのように扱えば法律上問題ないかを、資料を参考にして意見を書く問題 |
【総合:社会】
大問1は農業や資源に関する地理分野、 政治・外交に関する歴史分野、 日本国憲法に関する公民分野の融合問題です。
学校の教科書に記載されている内容を基本としていますが、 資料の分析力も必要となります。
また、 選択問題については「正しいもの」「まちがっているもの」を選択する形式が混在するので、 マーキングを行うなどしてミスを防ぐことが必要です。
大問2は2023年度入試と同様に資料を読み、 課題を思考し、 その課題を解決するための意見を記述する問題です。
総合(理科と社会に分かれる)で60分、30点満点。
大問2問、小問9問。社会にかけられる時間は30分程度で15点満点。
| 大問番号 | 小問数 | 出題内容 |
|---|---|---|
| [1] | 7 | (1)1800年代中ごろから後半にかけての日本のできごととして、まちがっているものを1つ選択する問題 (2)鉱産資源の輸入先のグラフを見て、鉱産資源として正しいものを1つ選択する問題 (3)イスラム教徒のくらしとして、正しいものを1つ選択する問題 (4)日本と外国の関係について説明したものを、古い順に並べかえる問題 (5)『あたらしい憲法のはなし』の文の空欄にあてはまる言葉を、ひらがな4字で答える問題 (6)日本の食料生産に関する3つのグラフを見て、読み取れることとしてまちがっているものを1つ選択する問題 (7)日本の水産業がかかえる課題について、グラフを参考にして会話文の空欄にあてはまる語句を答える問題 |
| [2] | 2 | (1)大阪万博が開催されたころ(1960年~1975年)に起こっていた「様々なひずみ」について、2つのグラフから読み取れることを、80字以上120字以内で説明する問題 (2)自分の「幸福な生き方」について、SDGsの目標から1つ選び、 目標の種類および選んだ理由と、その目標に関連して自分ができることを80字以上120字以内で説明する問題 |
面接
1グループ4~5名(男女混合)、15分間で実施(事前発表では10分程度とされていました)。10点満点。
「コロナ終息後観光客が急増したが、このことによる観光地への影響について、グループで話し合いなさい。」
過去の出題形式