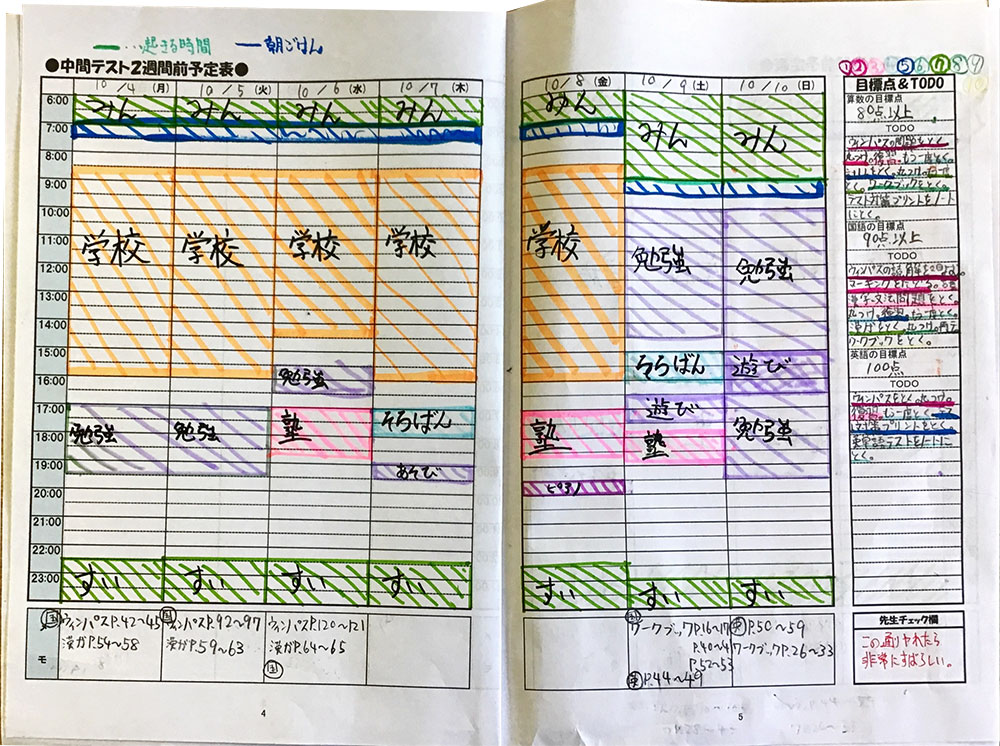奈良女子大学附属中等教育学校 令和7年度(2025年度)の出題傾向/出題形式について
奈良女子大学附属中等教育学校
出題傾向/出題形式
令和7年度(2025年度)一般適性検査
表現Ⅰ(国語)
国語領域の問題は大問2・3
(表現Ⅰ 100点満点(60分)/ 国語領域70点・社会領域30点)
1. 大問2:「文章の全体像」をつかむ力が求められる
「食と心理の密接な関係の存在」「雑食性動物である人間が持つ、食に対するジレンマ」「調理の役割」というように、話題が展開していく文章内容であり、その「展開」をつかむ力が求められました。
問2・4・5・6は、話題の展開を踏まえて「記述問題の解答材料の範囲」をつかむことが求められました。
また、問7については、文章後半の「ジレンマ」という話題に関連づけて自分自身で考察する必要がありました。
2. 大問3:「共通点の説明」「ちがいの説明」が復活した
例年、最後の設問は「自分の考えを述べる問題」です。
「〇〇という問題をどのように解決するか」という趣旨の設問が2年続きましたが、それ以前に頻出であった「共通点・ちがい」の説明問題が2025年度では出題されました。
さらに、その出題では、「共通点とちがいの『両方』を説明しなさい」との指示が出されたため、「一つのものごとを複眼的(多角的)にとらえる力」がためされたと言えます。
話題は「日本を訪れる外国人の期待」という時事的な話題でしたが、予備知識の必要はなく、提示された資料の適切な読み取りを求める設問でした。
| 大問2 (文章読解) | 本文内容 | 論説文(石川伸一『「食べること」の進化史』より) 内容:人間と「食」の関わり合いについての考察 「食」に関する人間の根源的心理について「人間が雑食性動物」であるという観点から考察する内容。 |
| 問1 | 漢字書き取り5問(小6配当漢字は2字で、 それ以外は小3~5配当漢字) | |
| 問2 | 傍線部の主語を文中から抜き出す問題(20~30字以内) | |
| 問3 | アナグラムの問題(「じょうぎ」を並べ替えて別の言葉に変える) | |
| 問4 | 傍線部の理由となる表現を文中から抜き出す問題(65字以内) | |
| 問5 | 傍線部の理由説明(70字以内) | |
| 問6 | 本文中のキーワードについて説明する問題(「調理」の果たす役割の説明) | |
| 問7 | 傍線部の理由を自分で考えて説明する問題 | |
| 大問3 (資料問題) | 「日本を訪れる外国人旅行者の旅行目的について述べた文章」と「外国人旅行者が日本に来る前に期待していたことの 資料(観光庁2023年報告書)」を示し、両者の「共通点」「ちがい」をそれぞれ説明する問題 | |
表現Ⅱ(算数)
算数領域の問題は大問1~大問4
(表現Ⅱ 100点満点(60分) / 算数領域70点・理科領域30点)
例年、グラフの読み取りまたは作図の問題、平面図形、規則性の問題がよく出されており、 2025年度もその傾向は大きくは変わりませんでした。
ここ数年、図形やグラフの作図と理由などを説明させる出題が続いていますが、2025年度は、理由を説明する問題とグラフの作図の問題は出されたものの、コンパスを使った図形の作図の問題は出されませんでした。
また、過去2年で出題されていた答えのみを書く問題が2025年度は出されず、答えが「ない」ことを説明する問題が6年ぶりに出されました。
問題の構成としては、大問で1つの問題になっているような問題が2題あり、これらの問題は配点が高かったと考えられます。
また、全体的に難化しており、答えにたどり着けなかった問題も多かったと思われます。そのため、解答用紙にわかるところまできちんと書き、部分点を取りにいくことができたかが重要でした。
さらに、近年は理科の内容の問題用紙が2枚になっており、2025年度は算数の内容が先に出題されたので、算数の問題を解くのに時間がかかってしまい、理科の問題を解く時間が足りなかった受検生も多かったと考えられます。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 1 | 容積 |
| [2] | 3 | 正六角形の面積の比(答えが「ない」ことを説明する問題あり) |
| [3] | 1 | 消去算 |
| [4] | 3 | 速さとグラフ(グラフの作図問題あり) |
表現Ⅱ(理科)
理科領域の問題は大問5〜大問6
(表現Ⅱ 100点満点(60分) / 算数領域70点・理科領域30点)
大問2問、小問6問。
算数と合わせて60分のため、理科にかけることができる時間は15分〜17分程度と想定されます。
2025年度の傾向として、「実験方法を説明する問題」「実験結果を考え、その理由を説明する問題」「実験結果や現象に関する理由を説明する問題」「実験結果をもとに、身近な現象が起こる理由を考える問題」など、「実験方法や結果、現象が起こる理由を考えて説明する問題」が多数出題されました。
これらの問題は、奈良女子大学附属中等教育学校の代表的な出題傾向であるとともに、得点差が大きくついた問題になったと考えられます。
また、ヘチマの雄花と雌花の図から雄花を選ぶ問題など、基本的な知識問題も出されるので、しっかり得点できるようにしておきましょう。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [5] | 3 | (1)ヘチマの花の図から、雄花を選ぶ問題 (2)花が咲く前に中庭のヘチマの雄花すべてにふくろをかぶせても、 雌花のいくつかに実ができた理由を説明する問題 (3)実ができるためには受粉が必要であることを確かめる実験方法を説明する問題 |
| [6] | 3 | (1)水を下から加熱すると、まず上があたたまり、やがて下の方にも伝わっていく 理由を説明する問題 (2)実験結果のグラフから分かることを2つ説明する問題 (3)実験結果を参考にして、池の表面の水だけが凍った理由を説明する問題 |
表現Ⅰ(社会)
社会領域の問題は大問1
(表現Ⅰ 100点満点(60分) / 国語領域70点・社会領域30点)
大問1問、小問が5問。
国語と合わせて60分のため、社会にかけることができる時間は20分程度と想定されます。
地理分野が2問、歴史分野が2問、公民分野が1問で、それぞれの分野の知識を活用して説明する形式で出題されました。
そのうち資料の読み取り問題が地理分野と公民分野でそれぞれ1問出題されています。
資料のデータや事実を適切に読み取る力、さらにそのデータや事実の背景について、知識と結び付け、適切な言葉を使い表現する力、抽象化されている問いに対して具体的な例を挙げて説明する力が求められました。
問題の難易度は標準的です。
地理分野(地理的な背景、環境対策)、歴史分野(鎌倉時代の社会、明治政府の政策)、公民分野(基本的人権)に関する知識を活用して、適切に説明できるかがポイントとなります。
| 小問番号 | 出題内容 |
|---|---|
| 問1 | 鎌倉時代の政治や社会の仕組みをふまえて、武士が武芸にはげんでいた理由を説明する問題 |
| 問2 | 国や国民を1つにまとめるために明治政府が進めた政策の内容とねらいを説明する問題 |
| 問3 | 図から読み取れる、スタジアム建設にふさわしい場所の条件と、その理由を説明する問題 |
| 問4 | 2021年、2024年に開催された東京、パリのオリンピック・パラリンピックで行われた、 環境への負担を減らすための具体的な例をあげる問題 |
| 問5 | バリアフリーに関する、「物理的なバリア」「文化・情報面のバリア」の解消方法をそれぞれ説明する問題 |
表現Ⅲ
表現Ⅲ:調査書10点満点+対話的表現10点満点(合計20点満点)
2025年度入試の「対話的表現」は、「グループ活動(25分程度)」で実施。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 5分間 | 6月に行われるスポーツ大会で応援に使う大きなクラス旗を作ることになった。 まず、話し合いをせず旗に書く「文字・図・色」などのデザインを一人で考えなさい。 (A4用紙・鉛筆・鉛筆削り・消しゴムが机に置かれている) |
| 20分間 | それぞれが考えた旗をグループで話し合って一つにまとめなさい。旗は完成しなくてもよろしい。 (A3用紙と12色の色鉛筆を配付される。) |
令和7年度(2025年度)連絡進学適性検査
表現Ⅰ(国語)
表現Ⅰは国語領域の問題。100点満点(50分)
1.「考えて書く」と「文中のことばを利用して書く」の2形式が基本
記述問題に関しては、「自分で(もしくは本文内容から)考えて書く」問題(問3・5・8)と、 「文中のことばを利用して書く」問題(問2・4・6・7)の大きく分けて2つの形式で構成されています。
前年は抜き出し問題が2問ありましたが、すべて記述問題でした。
最後の設問(問9)は毎年、「自分の意見文を書く問題」です。
前年の「自分の意見+その意見に対する反論+反論者を説得する意見」を求める問題にくらべると、「単純化」したと言えます。
2.多様な問題構成
「物語を素材文として作問できるすべてのバリエーション」ともいえる、多様な設問でした。
「心情説明」の設問においても、「直前のできごと」だけをとらえて解答できる設問だけではなく、ストーリーの展開を踏まえて主人公の心情変化をとらえなければならない設問もあり、「ミクロの視点・マクロの視点」の使い分けが求められました。
| 本文内容 | 物語(林芙美子「狐物語」より) 子狐を通して人間の有様を批判的に語る内容 |
|---|---|
| 問1 | 漢字の書き取り(5問) |
| 問2 | 心情説明(直前のできごとを踏まえて考える) |
| 問3 | 本文中のあいまいな表現(読み間違いが起こる表現)について、 ①読み間違いの可能性の説明、②読み間違いが起こらない表現への書き換え |
| 問4 | 心情説明(直前のできごとを踏まえて考える) |
| 問5 | 心情説明(できごとの展開を踏まえて考える) |
| 問6 | 登場人物の会話文(セリフ)の要約 |
| 問7 | 心情説明(できごとの展開を踏まえて考える) |
| 問8 | 本文中の情景描写の「表現効果」の説明 |
| 問9 | 資料(フェイクニュース・デマについての説明文)を踏まえて自分の考えを書く ①資料と本文の共通点の説明 ②フェイクニュース・デマにだまされたり、それらを広めたりしないために気を付けることについての自分の考え |
表現Ⅱ(算数)
表現Ⅱは算数領域の問題。100点満点(50分)
大問数は6問から7問に増え、小問数も15問と昨年よりも多かったです。
ただし、問題用紙は3枚から2枚になっており、答えのみを書く問題が2問出ていたので、時間が足りなかったという生徒はほとんどいなかったと考えられます。
(2022年度:大問7・小問14/2023年度:大問7・小問13/2024年度:大問6・小問13)
一般入試と違い、大問1で必ず計算問題が出されます。
昨年同様4問で、難易度もほとんど変わりませんでした。
また、一般入試と比べて大問数が多いので、さまざまな単元から出題されます。
ただし、グラフをかいたり、途中式をかく問題が出されたりするのは、一般入試と同様です。
最近の傾向として、一般入試と同じように「理由を説明する問題」がよく出されるようになり、問題の難易度も一般入試とほぼ差がない状態です。
2020年度 3問(消費税に関する問題・代表値の選択理由・同じ個数にならない理由)
2021年度 1問(概算を使った説明)
2022年度 3問(円周率の説明・円周率が3より大きいことの説明・概算を使った説明)
2023年度 出題なし
2024年度 2問(台形の面積の公式の説明・計算方法の考え方の説明)
図形やグラフの作図の問題、理由を説明する問題は出されませんでした。
ただし、大問2の速さと比や、大問7の平面図形の面積の問題などは、途中の式だけでなく、文章での説明も必要だったと考えられます。
その点では、例年と出題傾向に大きな変化はありませんでした。ただし、計算が必要な問題で答えのみを書く問題が2問出ており、連絡進学の入試問題では初めてのことです。
これは、この2年で一般入試の問題で見られた傾向であり、一般入試の問題を参考に作成されていることがわかります。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 4 | 計算問題 |
| [2] | 1 | 速さと比 |
| [3] | 1 | 食塩水 |
| [4] | 3 | 規則性 |
| [5] | 1 | 折り曲げた図形の角度 |
| [6] | 4 | 水量変化とグラフ |
| [7] | 1 | 平面図形の面積 |
表現Ⅲ
表現Ⅲ:調査書200点満点+対話的表現30点満点(合計230点満点)
2025年度入試の「対話的表現」は、「グループ活動(25分程度)」で実施。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 5分間 | 小学校の学習研究発表の際に来られた先生方に附小の魅力を伝えるために「附小の魅力」をグループで話し合う。 (人数分のA4用紙が配付される) |
| 20分間 | (追加課題)※A3用紙が4枚配付される 発表できるよう、A3用紙4枚すべてを使って内容をまとめる。(実際の発表は無し) |