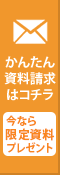奈良教育大学附属中学校
奈良教育大学附属中学校
傾向と対策〜算数編〜
皆さん、こんにちは!
奈良教育大附中作文模試まで、20日あまりとなりました。
今春の奈良教育大附中合格実績、52名(全国NO1!)を誇るKECゼミナールでは、豊富な情報で確かな信頼を得ているプロ講師陣が、附中の入試問題分析を行っています。
そこで今日は、算数・数学科主任の三ツ矢先生にお聞きした、「附中の傾向と対策(算数編)」について書かせていただきたいと思います。
中村「三ツ矢先生、奈良教育大附中の問題ですが、今年は出題傾向に変化があったそうですね。」
三ツ矢「そうなんですよ。例年は大問数が6題だったのですが、今年はなんと、8題になりました。」
中村「え?では、小問数も増えたのですか!?」
三ツ矢「いえいえ、出題の仕方が変わっただけで、小問数に変化はありません。」
中村「では、中身を教えていただけますか。」
三ツ矢「わかりました。」
まず大問1は、計算問題です。今年は3題出題されました。
4年生から6年生で習う、四則計算ですが、いずれも基本に忠実な問題です。
次に、大問2です。例年大問2は小問集合でしたが、今年は大問2以降が全て独立した問題に
なりました。
大問2は資料の読み取りに関する問題が出題されました。ここ数年では珍しい出題でした。小学6年生で習う内容ですので、現時点で皆さんが解くのは少し難しいかと思いますが、学校や塾の授業を大切にしていれば十分完答できるレベルですね。
大問3は売買に関する問題で、割増・割引がわかっていれば問題ないレベルです。
大問4は容積に関する問題です。水そうの中に物体(ブロック)が入っているという設定
なので、少々難しいかもしれませんが、体積の求め方がきちんと理解できていれば問題
ありません。
大問5は小問集合3題が出題されました。(1)は数と数の間に「+−×÷」を入れて、式を完成させる問題でした。(2)は和や差に関する問題、(3)は倍数・約数に関する問題でした。(3)は少々難しく感じる受験生もいたかもしれませんね。
大問6は速さとグラフに関する問題でした。昨年は, 初めて目盛りのないグラフが登場しましたが、今年は一昨年までのような、目盛りつきのグラフに戻りました。グラフを書けば解けるので、「ていねいに」書くことさえ心がければ、処理できる問題でした。
大問7は平面図形, 大問8は立体図形に関する問題でした。どちらも少々レベルが高く、難しく感じた生徒もいたでしょうね。
小6の内容だけでなく、小4・小5からの出題もかなりありますので、「受験勉強は小6から...」という感覚は捨てて、苦手な単元から順番に克服していくことが望ましいですね。
「速さとグラフ」・「平面図形」・「体積と容積」については、「附中の入試で毎年必ず出る問題」です。
満点は20点ですが、もちろん算数が苦手なお子さんも、「これだけはとっておかなければいけない!」という問題はあります。
KECゼミナールでは、そのあたりのことを詳しく指導しています。
中村「これから入試に向けて、どのようなことをしておけばいいですか?」
三ツ矢「教科書レベルの問題については、どのような分野においても正解できるような
力をつけておく必要があります。
これから夏に向けて書店で発売される「赤本」の問題を実際に解いてみて、できなかった問題を何度も繰り返し演習することが大切です。
そのうえで浮き彫りになってきた苦手単元を何度も繰り返し解くことで、解説を見なくても解ける力をつけていきましょう。」
中村「三ツ矢先生、ありがとうございました!」
皆さん、いかがでしたか?
算数は、一つでも苦手分野をなくすのが大切であるということが、よくわかっていただけたのではないかと思います。
今後も、傾向と対策についてのインタビューが続く予定ですので、お楽しみに...!